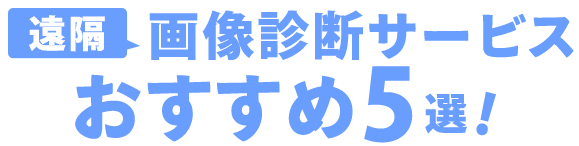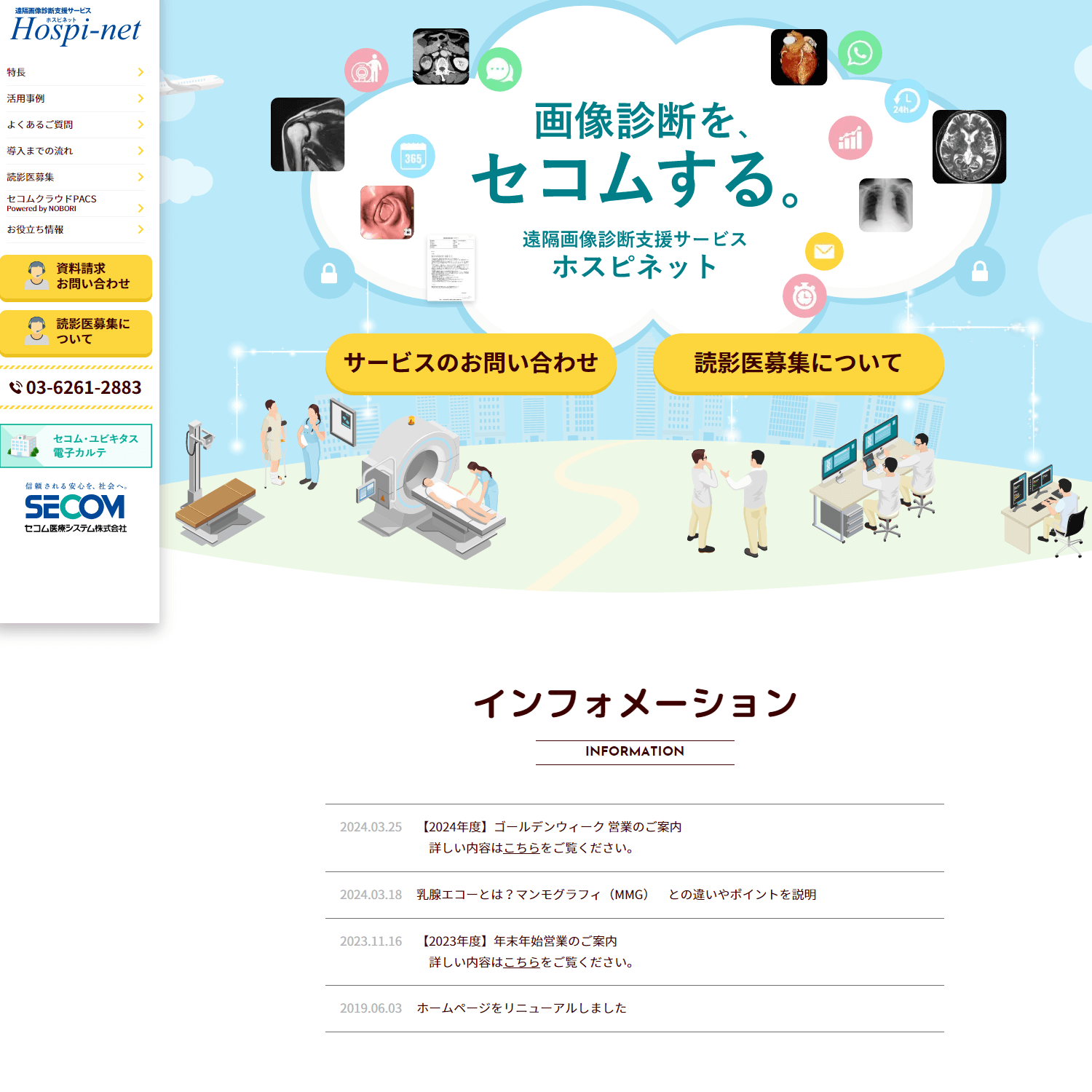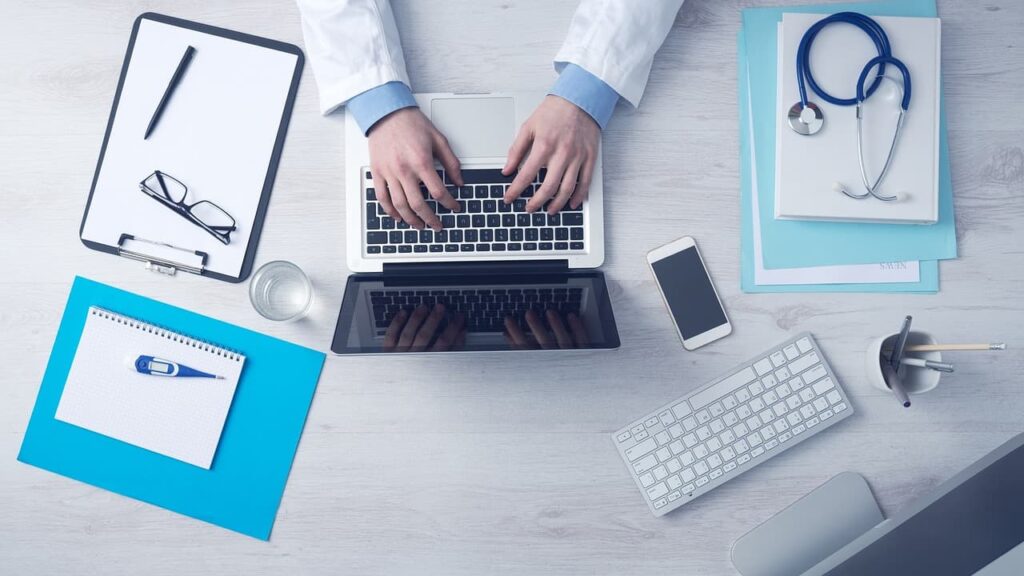医師及び医療従事者の多忙さは年々増しており、業務改善に取り組まなければならないケースも多いことでしょう。そんなときは遠隔画像診断を導入することで、院内の負担を軽減可能です。本記事では、遠隔画像診断の概要やメリット・デメリットを詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
遠隔画像診断とは
遠隔画像診断とは、ICT(情報通信技術)を活用して、CTやMRI、核医学検査などで得られた放射線画像を、撮影した医療機関とは異なる場所で読影・診断を行う仕組みです。医療機関で撮影された画像を、放射線診断専門医が在籍する提携医療機関や外部の遠隔診断サービス事業者に送信し、読影や診断を依頼する形で運用されています。この仕組みにより、医師が常駐しない医療機関や医療過疎地域でも質の高い診断を受けることが可能となりました。
とくに、放射線科医の不足に悩む施設や専門外の分野での読影機会が多い医療機関、また働き方改革を進めたい施設にとって有用とされています。日本ではCT・MRI装置の設置数が世界的に多い一方で、稼働率の低さが課題とされがちです。そこで遠隔画像診断の導入によって読影業務の分担が進むことで効率的な検査運用が可能になると期待されている。
また、医師の業務負担を軽減し、読影を外部に委託することで時間的余裕を確保できる点もメリットといえます。2019年度の調査によると、遠隔画像診断は主にCT/MRI(45.6%)と単純X線(胸部)(32.1%)で多く利用されており、肺炎や肺がんなどの診断、腫瘍や脳血管疾患の評価など幅広い分野で活用が進んでいます。一方で、乳がん検診用のマンモグラフィやPET-CTなどの利用率は低く、今後の普及が課題といえるでしょう。
遠隔画像診断のメリット
遠隔画像診断の導入には、医療現場におけるさまざまな課題を解決する多くのメリットがあります。
医療の質の向上
まずもっとも大きな利点は、医療の質の向上です。CTやMRIなどの放射線画像は診断の正確性が求められる分野であり、読影の誤りは患者の命に関わる可能性もあります。遠隔画像診断を導入することで、放射線診断専門医による高精度な診断が可能となり、より質の高い医療提供につながります。
医師不足の解消
次に、医師不足の解消が挙げられます。とくに地方や医療過疎地域では、放射線診断専門医が不足しているケースが多いですが、遠隔画像診断を活用すれば距離に制約されずに専門医の診断を受けることが可能です。
また、読影業務を外部に委託することで、現場医師の業務負担も軽減され、限られた人員でも効率的な診療が可能となります。
多様な働き方の実現
さらに、多様な働き方の実現にもつながります。読影依頼側の医師は診断業務の一部を外部に委託することでほかの診療や研究に時間をあてられ、読影を行う医師は自宅など場所を問わず柔軟に働くことができます。
ICTを活用したオンライン環境が整備されつつある現在、放射線科医の働き方改革にもつながっているのです。
検査機器の稼働率向上
検査機器の稼働率向上も重要なメリットです。日本は世界的に見てもCT・MRIの設置台数が多いですが、読影負担や人員不足により十分に活用できていない施設もあります。遠隔画像診断の導入により診断プロセスの効率化が進み、機器の稼働率向上や医療資源の有効活用が期待されます。
紛失リスクや情報漏洩リスクの低減
紛失リスクや情報漏洩リスクの低減も見逃せません。最新の通信技術と厳重なセキュリティ対策により、データを安全に送受信できます。郵送や物理メディアでの受け渡しと比べても、リスクは大幅に低く、ガイドラインにもとづいた安全な運用が可能です。
遠隔画像診断のデメリット
遠隔画像診断の導入には多くの利点がある一方で、いくつかのデメリットも存在します。
導入・維持のコスト
第一に挙げられるのは、導入や維持のコストです。遠隔画像診断を実施するには、通信環境の整備やPACS(画像保存通信システム)などのシステム構築が必要不可欠であり、情報漏洩対策も徹底しなければいけません。そのため、初期費用だけでなく、システムの保守・運用・管理にかかる月額費用や読影依頼に応じたコストも継続的に発生します。
サービス提供企業によって料金体系が異なるため、導入を検討する医療機関は、自施設の検査件数や運用体制に適したサービスを慎重に選ぶ必要があるでしょう。
セキュリティ面のリスク
次に懸念されるのが、セキュリティ面でのリスクです。遠隔画像診断では、患者情報や検査画像をインターネットを介して送受信するため、不正アクセスやサイバー攻撃による情報漏洩の危険性が常に存在します。より安全性の高い専用回線を使用する方法もありますが、その分、通信費用が高額になる点が課題となります。
日本医学放射線学会では安全運用のためのガイドラインを策定しており、各医療機関はその内容を遵守してセキュリティ対策を講じることが求められるでしょう。
提携する医療機関・事業者を探す必要がある
さらに、提携する医療機関・事業者を探す必要があるという点もデメリットのひとつです。実際の調査によると、遠隔画像診断を依頼する医療機関は多い一方で提供側は限られており、提携先の選択肢が少ないのが現状です。
外部の遠隔画像診断支援サービスを利用する場合も、費用や診断精度、対応速度、サポート体制など事業者ごとに特徴が異なるため、信頼性の高いパートナーを慎重に選定する必要があります。
まとめ
遠隔画像診断は、ICT技術を活用して医療の質と効率を大きく高める仕組みです。専門医の診断を距離に関係なく受けられるため、医師不足の地域でも高度な医療提供が可能となり、医療現場全体の負担軽減や働き方改革にもつながります。さらに、検査機器の稼働率向上や情報漏洩リスクの低減といった利点も魅力です。一方で、導入や維持には一定のコストがかかり、セキュリティ対策や信頼できる提携先の確保など課題もあります。しかし、これらを適切に管理すれば、遠隔画像診断は医療現場の未来を支える有力なソリューションとなるでしょう。